| |
風 車 |
形 状 |
性 能 |
摘 要 |
 |
 |
材質 外装用の合板
形状 6枚羽根
半径 60Cm
幅 20Cm
ひねり角 20°
全翼面積 3660c㎡
発電機 ハブダイナモ
6V-2.3W |
3m/s程度の風が吹けば、毎分120回転は回り、交流6Vの電圧が得られる。これを倍圧整流して12Vのバッテリーに接続すれば、わずかだが電流が流れて充電できる。 |
手元にあった材料で、最初に製作した風車です。羽根の取り付けには、25mmの角材を使っています。
12年12月の突風の時、取り付け方がしっかりしてなくて、羽根が支柱に接触して破壊しました |
 |
 |
セールウイング型
6枚羽根
半径50Cm
ひねり角不明
総翼面積 4150c㎡
発電機 ハブダイナモ
6V-2.3W |
2m/s程度で起動
2.5m/s程度で充電を 始め、4m/s〜4.5m /sで220mAで頭打ち
(倍電圧整流) |
製作が比較的簡単で、動バランスも取りやすい。水道用の塩ビ管とステンレスのワイヤを使用している。
布を取り替えながら、現在も元気に発電しています。 |
 |
 |
材質 硬質塩ビ
4枚羽根
半径 50Cm
ひねり角は
中央部20度
先端部10度
総翼面積 3200c㎡ 発電機ハブダイナモ
6V−3W型 |
5,6枚羽根に比べて、起動制は劣るが、5m/s程度の風になれば、回転数は大きくなる。 |
羽根の取り付けは、水道用の塩ビ管。
H14年2月、強風で塩ビのパイプが折れて、羽根が1枚破壊したので、取り外しました。 |
 |
 |
材質 2㎜アクリル
形状 5枚羽根
半径 50Cm
ひねり角は
中央部20度
先端部10度総翼面積 3230c㎡ 発電機 ハブダイナモ
6V−2.4W |
起動制は、4枚と6枚の中間 |
羽根の取り付けは、水道用の塩ビ管。
手元にあった寄せ集めのアクリル板で、厚みや大きさが違う物もあって、動バランスが悪くて、回転数が上がると振動しだすので、現在は取り外している。
|
 |
 |
材質 2㎜アクリル板
形状 6枚羽根
半径 50Cm
ひねり角は
中央部20度
先端部10度
総翼面積 3100c㎡
発電機 ハブダイナモ
6V−2.4W |
起動制は一番よい。2m/s程度の風でも回転を始めるが、充電が始まるのは2.5m/秒程度から。 |
羽根の取り付けは、水道用の塩ビ管。
5号風車同様寄せ集めの材料なので、現在は取り外している。 |
 |
 |
「かざぐるま型」
0.5mm厚の塩ビ版
600mm×600mm
発電機 ハブダイナモ
6V−2.4W |
3m/s 程度の風で 140回転程度回り、100mA程度充電。
風力発電用としてはほとんど使われていないが、実用になりそうだ。 |
ダイナモへの固定は、100mmの排水用塩ビ管で、中央のパイプの長さでかざぐるまの厚みを調整します。
13年12月の突風で破損した。0.5mm厚の板では強度が不足。 |
 |
 |
材質 1.5㎜塩ビ板
形状 8枚羽根
半径 35Cm
折り曲げ角は45度
総翼面積 2800c㎡
発電機 ハブダイナモ
6V−2.4W |
1.5m/sで起動、
2m/sで充電開始
4m/sで150mA
5m/sで230mA
で頭打ち
(倍圧整流の場合) |
半径35Cmでは小さすぎた。半径40Cmぐらいにすれば、4〜4.5m/s程度で頭打ちになるのではないかと思われる。
強風で破損しました。 |
 |
 |
材質 1.5㎜塩ビ板
形状 12枚羽根
半径38Cm
ひねり角17度
総翼面積 2760c㎡
発電機 ハブダイナモ
シマノインターL |
1m/sで起動、
2m/sで充電開始
4m/sで220mAで頭打ち
(倍圧整流の場合)
|
羽根の取り付けは、水道用の塩ビ管。
1m/s程度の弱い風でもよく回る。
8m/s程度の風でも問題なく回っている。 |
 |
 |
材質 1.5㎜塩ビ板
形状 6枚羽根
半径45Cm
ひねり角17度
総翼面積 3150c㎡ 発電機 ハブダイナモ
6V-2.4W |
2m/sで起動
2.5m/sで充電開始
4m/sで230mAで頭打ち
(倍圧整流の場合)
|
羽根の取り付けは、水道用の塩ビ管。
8,9号の羽根は、塩ビ板を熱湯に浸けて柔らかくして、そりを付けて、強度を大きくするように工夫してみた。
|
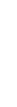 |
 |
材質 ラワン材
形状 半径60Cm
幅 12.5Cm
ひねり角
中心部 12°
先端部で4°
総翼面積 2250c㎡
発電機 ハブダイナモ
6V-2.4W |
3〜3.5m/sで起動
いったん回転を始めると、3m/sでもよく回り、200mA
4m/sで270mA
5m/sで330mA
(全波整流の場合) |
これは、試作3号のブレードですが、動バランスが悪くて振動している。
回転を始めると、すぐに回転数は大きくなるので、この風車では倍電圧整流よりも全波整流の方が有利なようです。
突風で、溶接部分が破損して支柱に接触し、ブレードも破損しました。
|













