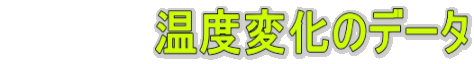
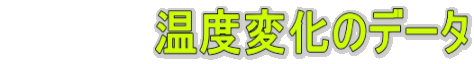
| 竹(孟宗竹、破竹)を中心にドラム缶釜で30回ほど焼いてみて、炭焼きのポイントをまとめてみました。 ① 自燃が始まったタイミング |
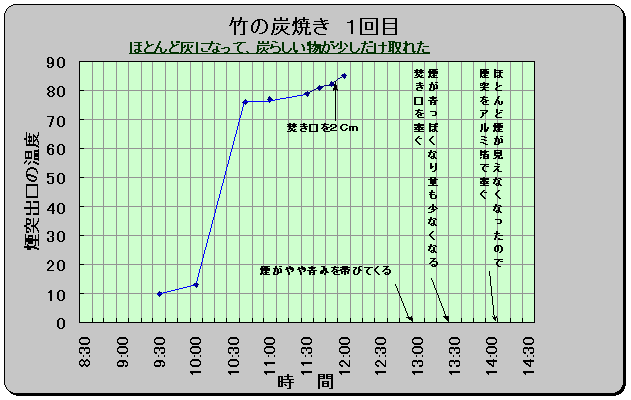
|
* ほとんどが灰になって、炭が少しだけ取れました。 |
|
平成12年12月8日、第2回目の炭焼きを実施しました。 2回目からは、200度の温度計を使用しました。 |
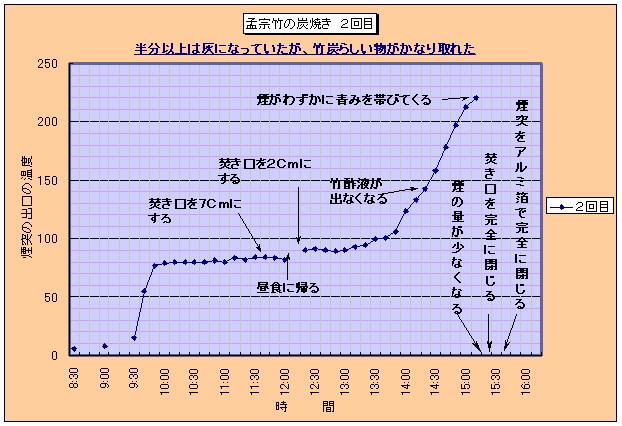
|
* 今回も、いつ自燃に入ったのかがよく分からなくてずるずると焚き続けて、11時40分に燃料の補給をやめて、焚き口を7Cm(140平方Cm)にしました。半分以上が灰になっていたので、もっと早く焚くのをやめて、焚き口を小さくしてもよかったのかな。 平成12年12月12日、第3回目の炭焼きを実施しました。 |
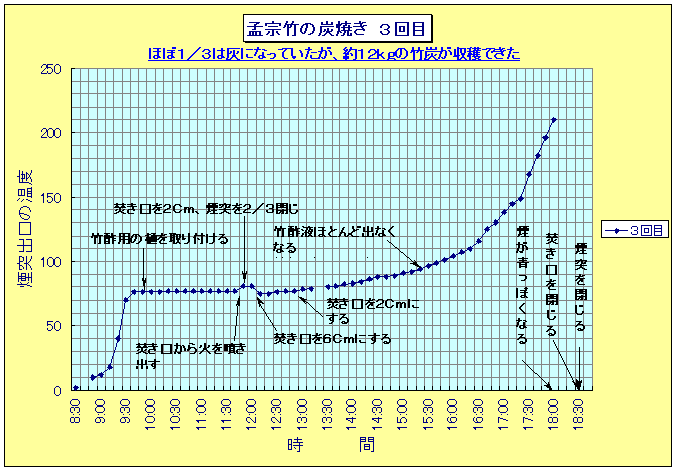
|
本格的な窯で炭焼きをしている先輩から、自燃が始まると焚き口から火を噴き出してくるという話を 聞いたので、今回は気をつけて観察してみた。11時40分頃に火を噴き出したように見えて、温度が上がり始めたので、煙突を2/3閉じ、焚き口を2Cmにした。急に温度が下がりだしたので、焚き口を6Cmにするとまた温度が上がり始めたので、1時間後にまた2Cmにしてみた。 平成13年1月12日、第4回目の炭焼きを実施しました。 |
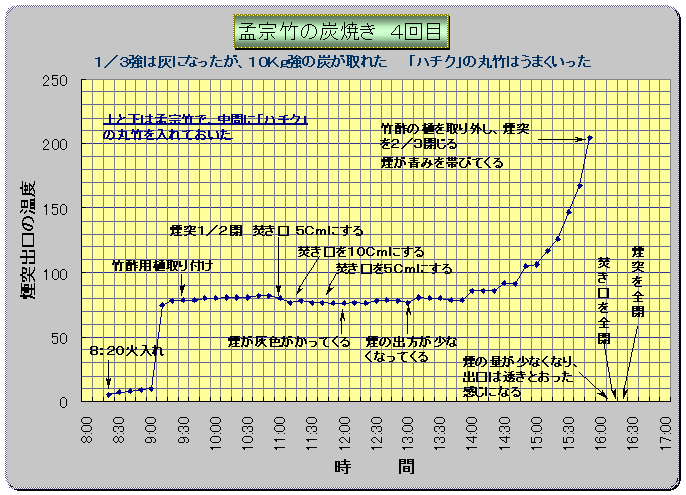
|
自燃に入ったタイミングはやはりよく分からなかった。途中で焚き口の開け具合を調整してみたが効果は分からない。全部が完全に炭になっていたので、完全に閉じるタイミングは良さそうである。
平成13年1月21日、第5回目の炭焼きを実施しました。 |
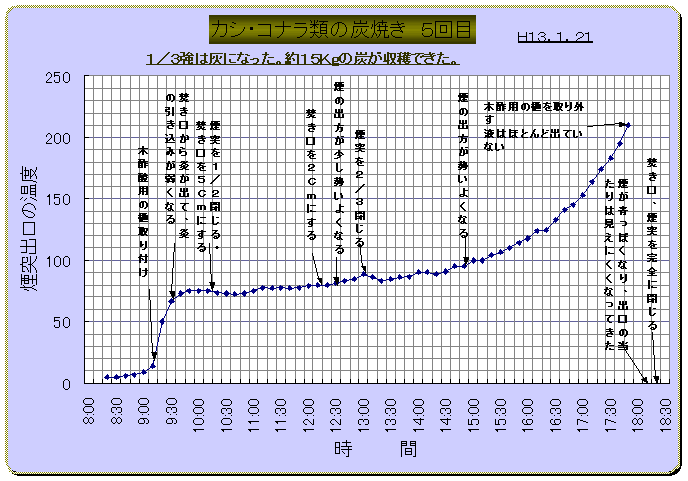
|
温度が70度を超えて、安定してきたら自燃に入っているのではないかと思われたので、(9時30分頃、焚き口から炎を吹き出してきたように見えた)前回までとは早めに焚き口と煙突を絞ってみた。じわじわと温度が上がり続けたので、途中で焚き口を2Cmに、煙突を2/3閉じた。 平成13年2月3日、第6回目の炭焼きを実施しました。 * 5回目を基本に、ほぼ同様の過程で焼くことにした。 |