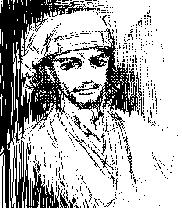 |
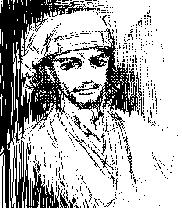 |
|
(一)
文若と出会ったのは、初めて曹公に謁見した日のことだった。 中原の風が苦手だ。古傷に滲みるのだ。 曹公のお膝元、許都。 謁見の間からのかえり、吹き貫きの回廊で膝の痛みに襲われた。 「どうなさいましたか」 うずくまり痛みを堪える私にかけられた声。振り返ると、彼が立っていた。 菖蒲の香がかおった。洗練された都会的な雰囲気。一見質素かとも思える衣服の布地は、極上のものだ。面に薄く載せられた白粉が少しも嫌味ではなかった。 「ご心配なく。古傷が痛んだだけです。・・・・・・これは荀令君」 「わたしをご存知でしたか、元直殿」 彼は親しげに微笑み、手を差し伸べた。 「さきほど曹丞相と一緒にいるところをお見かけしました。・・・・・・ツツ」 「まだ痛みますか」 「いや、たいして。お気になさらず」 「元直殿、わたしはあなたを知っていますよ。同じ潁川(えいせん)の出身です。推挙したくて幾度か捜したことがありますが、あなたは上手に行方をくらませてしまって」 「推挙? 荀令君、ご存知のように私は単家(身分の低い家柄)の出身で、犯罪者です」 「それがなにか? 元直殿、曹丞相とはお会いになりましたよね」 「今、会ってきたところです」 私は頷いた。彼の言いたいことはわかった。曹公は人材に過去を問わないのだ。有能なら、敵であった者でも前科者でもかまわない。むしろそういった者を好 む癖があるようだ。あの手この手で、隠れた人材を捜し出しては仕官させることにやっきになっている。私もそうしてやって来た一人だ。 「母君はお元気ですか」 荀令君はサラリと言って私を見た。 「おかげさまで」 おかげさまで。嫌味に聞こえたかもしれない。だが、そうではなかった。事実、老母は城内の舘で何不自由なく元気に暮らしている。 「元直殿、よろしかったら今宵、一献酌み交わしませんか。同郷の朋(とも)として」 「荀令君、私ごときと、畏れ多いことです」 「令君はやめてください」 彼はそう言って笑った。 「文若と呼んでください」 気さくな人だと思った。あるいは彼は、私に擦り寄ることを曹公に命じられていたのかもしれない。だが、悪い気はしなかった。感じのよい彼の笑顔は、まるで宝石かなにかのように思えた。 荊州の山中で諸葛孔明らとともに遊学していた私は、ふとしたことで新野に駐屯していた劉玄徳将軍の客将となった。そのために北の曹公に身元がばれた。人 材を求めてやまない彼は、私の母を捜し出し捕虜にすることで、私を劉将軍から引き離し自分のもとに仕官するよう仕向けた。漢としての魅力があり、気持ちの あたたかな劉将軍には心を引かれたが、もともと私はだれにも仕官する気はなかった。母とともに静かに暮らせるなら、北に落ち着くのも悪くはないと思った。 仕方なしにではあったが、いやいや来たわけではない。 二人の君主が私を取り合ったことが滑稽だった。流れ者の私に漢王室の未来を熱く語って聞かせる劉将軍も、そんな手段にうったえてまで会ったこともない私 を得ようとする曹公も。二人の熱っぽさはよく似ている。彼らは面識があり、劉将軍は曹公のこともよく話題に出した。曹公のことを語るときの劉将軍は、漢王 室の理想について語るときと同じくらい、いきいきとして見えた。面白いことに曹公もまた、ひどく楽しげに、なつかしそうに宿敵劉備のことを語る。 荀令君は舘の二人きりの酒席に私を招いてくれた。 「帯剣なさらないのですか。元直殿は撃剣のつかい手と聞きましたが」 丸腰の私を見て、彼はたずねた。 「剣客だったのは十代のころですよ。心におもうところがあって、剣は棄てたんです。もう、十年以上も昔の話です」 「人を殺めたくないと」 「それもありますが、過去を捨てるにはその方法しかないと思いました。それと、母が悲しむので」 「そうでしたか・・・・・・」 彼はそれ以上私の過去には触れず、かわりに自分のことをしゃべった。 「わたしは武芸の方はからきしなのです」 はにかむように笑う。 「文若殿と武芸・・・・・・繋がりませんな」 「そうでしょう。文官でも、自分の身を守れるくらいには剣がつかえたほうがよいと曹丞相が言うので、夏侯元譲将軍に稽古をつけてもらったことがあるのです」 「ほう」 「将軍は根気強く教えてくださいました。でもわたしがなかなか上達しないので気を遣わせてしまって。将軍には、かえって気の毒なくらいでした」 「それは、大切な荀令君に剣術を教えるとなれば、たいへん気も遣うでしょう」 「それが、お恥かしい限りなのですが、自分で自分の太腿を斬ってしまう事件というのがありまして」 「あちゃー、やってしまったのですか」 私は苦笑した。 「ええ、それはもう、サックリと」 「夏侯将軍はあわてたでしょうな」 「その場では流石将軍、落ち着いたものでしたが、後で蒼い顔をして丞相に謝罪しに行くというのを引き止めるのに苦労しました」 彼は本当によく笑う。 光るものがこぼれるような笑顔は、酒気を帯びるほどに、さらに艶やかになっていく。 その夜、私たちは何度も乾杯し、他愛ないおしゃべりで盛り上がった。 北の地に帰って来てはじめて、私はしんからくつろいだ気分になった。 帰宅すると、母が寝ずに待っていた。 「お母さん、ぼくは遅くなるって言ったんだから、先に寝ててくれればいいのに」 「元直の顔を見ないと一日が終らないからね。それに、灯りのない家に帰ってくるのは寂しいものだろう」 「使用人は?」 「暇を出した。だっておまえ、あの人たちに家のことをまかせたら、母さんの仕事がなくなっちまうじゃないか。退屈はごめんだよ」 「あいかわらずだね、お母さんは」 「こんな広い家はいらないねえ・・・・・・」 それから私は、荀令君がとても感じのいい方で、男前だったということを話した。 「ふうん。元直より?」 「次元が違うよ、お母さん。ぼくが白粉なんかつけたら気色悪いだけだろ」 「母さんはそんな男は好かないね。男は太陽に肌をさらすもんだ。いい色に焼けてなんぼだからね」 「でも、彼の場合は似合ってるからゆるせるよ。お母さんにも見せたいなあ。本当に美男なんだ。いままで会ったなかで、文句なし一等美男だ」 「それよりおまえ、今日は曹公に会ってきたんだろう。どうだった?」 そのことをすっかり忘れていた。 「うーんと、思ったより小柄だった。それと、思ったより話しやすかった」 「あの人、おもしろい人だろう」 「おも・・・・・・、お母さーん、怖い人なんだぜ、ほんとは」 「そんなことくらいわかってるさ。だてに歳はとっちゃいないよ。まあ、あたしの見たところによると、なんでも自分の思い通りにならないと我慢ができない頭のいいぼうや、ってところだね、あの男は」 「ぼ・・・・・・」 「かかってきなさい」 「・・・・・・そろそろ休ませていただきます」 当たってるかもと思いつつ、私は頭巾をとって頭をクシャクシャと掻いた。 「あ、そうだ。明日配属の通知が来るって。いきなり思い通りの役職につけるかどうかは分からないけど、できる限り本人の希望に添うようにするからって」 「はいよ。おやすみ元直」 「ん。おやすみ。お母さんも、はやくおやすみ」 床に就いて目を閉じると、文若殿の白い笑顔が瞼の裏に広がった。 眠りがしのびこむにつれて、その顔は孔明になった。あの二人はどこか似たところがあるだろうか。ぜんぜん似ていない。ただ、きっと、強く印象に残っているからだろう。 孔明。彼は難民だった。戦火のなかを、幼い弟妹を連れて、逃げて、逃げて、逃げて、荊州の山奥までやってきた。弟妹に食わすために畠を開き、なんとか自給自足ができるまで。 逃げて、逃げて、逃げて、逃げて 農のうたをうたい 「元直も逃げてきたの? じゃあオレと同じだね」 同じだなんて言うもんじゃないぜ、孔明。きみは弟妹を守り抜いたんだ。胸を張っていけばいい。俺はダメさ。自分を消すことばかり考えてる。いつだって隠れちまいたいんだ。泥の中がお似合いでね。 「人を殺したから?」 自分が嫌いなんだ。とにかく嫌いなんだ。いくら学問しても無駄に思えてくる。 「オレは元直のこと、大好きだけどな」 おまえ、知らないんだよ。殺したやつのこと、なんとも思わないんだ。母さん引きずりまわして、逃げることしか考えなかった。あ、足手まといでさ。 「過去を捨てたいの?」 何度も捨てていこうと思ったんだ。 「お母さん、元気にしてるじゃないか」 十日で髪が真っ白になって。 「今は黒にもどってる」 過去を捨てたいんだ。もう、話すのはやめるよ。 「でもね、元直」 もうやめる。 一度捨てた自分の過去は、いつか必ず自分のもとにもどってくるんだよ 仕官なんかしないさ それが孔明の口癖だった。彼はちょっと独特だったのだ。雰囲気・・・・・・かな。 茶色く日に焼けた長い髪をかきあげながら、焦点の定まらない笑みを浮かべ、そのくせことさらにきっぱりとした口調で。 「オレ? オレは仕官なんかしないさ」 公威のやつがそれを真似してさ。俺たちの間で流行ったんだ。農道でばったり出くわしたりしたら。 「仕官なんかしないさ」 声を合わせてそう言って爆笑したものだった。 お遊びだ。 「ねえ元直。この地はなんてみずみずしくて平穏なんだろうね。オレは荊州に来て、はじめて人間になった気がしているよ」 ああ。 ああ、そうだな孔明。 俺たちずっとここにいような。仕官なんかしないでここで暮らそうな。ずっとこの荊州の豊かな自然のなかで、下界のことなんか忘れてさ。ずーっとここで、 ずーっと、いっしょに、暮らしていこ 静かだった。 すこしして、小鳥のさえずりが耳に入った。うるさいくらい。私はひとつ大きく息を吸って、はいた。自分がどこにいるのかわからなくて、しばらく混乱した。 「朝だ。いい天気だ」 窓を開けて身をのりだした。空が湖面のように澄んでいて、青い空気が少し肺に痛かった。 「仕官なんかしないさ」 と呟くと、私は急にせつなくなって、涙をこぼしてしまった。 その日のうちに印綬を授かり、翌日から出仕することになった。 (二) おや? 「・・・・・・・・・・・・」 曹公の姿が見えたような気がした。 私はのびあがって窓の向こうに目を凝らしてみた。姿は見えなかったが、やや間をおいて、豪快な笑い声が聞こえてきた。それから怒鳴り声、続いてなにかを命令する声。 「丞相が来てる。聞いてないぞ〜」 しぶしぶながら、私は執務室を出て挨拶に向かった。 「元直! おお、ちょうどよい。ついでがあったのじゃ」 曹公はいつ見ても若々しい。そして、職人みたいに動きやすそうないでたちをしている。彼といると、そのきびきびとした動作で周囲が止まって見えるくらいだから、好きになれないまでも感心してしまう。 曹公はキリッと私を見上げて言った。 「そなた、諸葛亮を知っているな?」 一瞬、返答に迷った。知らぬふりをしたほうがいいのか? だが、彼の強い眸がそれは無駄だと物語っていた。おおよそ彼はとっくに調査済みなのだ。 「よく知っております。親友だったと言ってもいいと思います」 「よし。ちょっと来い、話がある」 曹公は適当な一室を選んで入った。 「座れ」 椅子を引いて先に私を座らせる。こういうところは意外にこまやかな方だ。 「劉備のやつが軍師を得たそうな。その名は諸葛亮。字は孔明」 「ほう。ついに孔明も仕官しましたか」 「親友と言ったな、元直」 「遊学の友です。孔明は農を営みながらもよく学問に通じ、ともに語り合いました」 「同じ水鏡先生の門下か」 「はい」 曹公は心持ち眼を細めた。 「して、孔明とはどういう人物だ」 「ものごとの大要をつかむのが得意でした。若いのに、どこか飄々として、仙人じみたところがありました。中原から荊州に疎開してきた孤児で、実は、たいへんな苦労人なのですが」 「どんな顔をしておる」 「目鼻立ちにあまり特徴はありませんが、とにかく背が高いのです。なかなかの好青年といった感じです」 「ふーむ」 と曹公は言った。 「話を聞くに」 眉根を寄せて考える。 「わしの好みだ。玄徳などにはもったいない。・・・・・・孤児だと?」 「はい。丞相、私に使ったような手は彼には使えませんぞ」 「根に持っておるのか、元直」 「いいえ」 「ああ〜っ、もったいない」 曹公は頭を抱え込んで唸った。私は苦笑した。 「話題を変える。元直、荊州侵攻の話だが」 「は」 私はつい身構えた。彼のこの話の切り換え方についていくのは難しい。 「どうしても従軍してはくれぬか」 「丞相、勘弁してください。荊州には知人が多いのです」 「土地勘があるものは一人でも多くほしいのじゃ」 「それはわかります。ですが」 「頼む」 「丞相・・・・・・」 「どうしてもダメか?」 「丞相、私は軍事に参与できません。したくないのです」 思わず挑戦的な態度をとってしまった。 「・・・・・・」 曹公は上目遣いに私を見て唇をとがらせた。 「ふーんだ。あっそう。わかった! だったらこっちから願い下げじゃ。遠征にやる気のないものを連れて行くくらい、無駄なことはないからな」 「いや、失礼。尊大な口を」 「そういえば元直、おぬしその歳でいまだ独身だそうではないか」 なにが『そういえば』なんだ。 「ハァ・・・・・・。まあ、そうです」 「信じられん。常日頃から母孝行なやつと感心しておったが、肝心なところが抜けておる。母親に孫の顔も見せてやらんのか」 「それを言われると痛いですな」 「どこぞに気になる娘はいないか。領内のものなら話をつけてやるぞ」 「いや、これといって」 「女に興味がないのか。男のほうがいいか」 「いや、どちらかというと女性のほうが」 曹公はうつむいてフフッと微笑うと、立ち上がった。一緒に立とうとすると、私の肩に手を置いて立ち上がらせず、「まあまあ、きみは職務に励みたまえ」と言った。 「・・・・・・?」 「おおそうじゃ。文若からおぬしに伝言があった。『よかったら、またいつでも遊びに来てください』とな。おぬしのことが気に入ったみたいじゃ」 「それは、光栄にございます」 「ん」 それなり、曹公は足早に部屋を立ち去ってしまった。 「あのー、丞相、ここ私の執務室と違うんですけど」 私は苦笑した。 (三) 「おじゃましま〜す」 ある日、意を決して文若殿の舘に遊びに行った。 「おおー、元直殿、よく来てくださいました。実は・・・・・・」 客間に通されて、私はドキリとした。曹公がいた。 「おお、元直。来たか来たか。ま、坐れ」 初夏のうららかな日だった。開け放たれた窓から射し込む陽光が、虹色にきらめいていた。 文若殿はあいかわらず感じがよくて清楚で美しい。 曹公は青い単色の衣を着て、大きな琴の調律をしていた。 「勤務外で会うのは初めてだな、元直」 曹公はチラリと顔を上げて言った。 「そうですな、丞相」 「勤務外だぞ。字で呼べ。孟徳だ」 「ハハ・・・。元直殿、孟徳さま、どうぞごゆるりと。酒を持たせます」 文若殿が歩くと、シュッシュッと衣擦れの音がした。 ピィーン、ズィーン、ロンロンロン・・・・・・。琴の音が響く。 背筋をスッと伸ばし、両手を大きく構え、音取りをする曹公。身長八尺もあるノッポの孔明に見慣れた私の瞳には、彼の姿はひどく小さく映る。これが中原一帯を征した男の姿なのかと思うと意外だ。 「元直、おまえやる気ないだろう。八門金鎖の陣を見破り、我が軍を散々に蹴散らしてくれた男が、なんで民政の小役人希望なんだ」 曹公が鋭い視線を投げかけた。鋭くて、影がある。 「玄徳に義理立てしておるのか」 「いいえ。私はただ、静かに暮らしたいのです」 無数の者を手にかけてきた惨忍な男の影が曹公にはあったけれど、私は彼を怖いとは思わなかった。彼が私を殺す理由がないからだ。そんなことをすれば世間に噂が広まり、人材が集まらなくなる。誰よりも彼が一番、そのことをよく知っているはずだ。 だが、それだけではなかった。そんな理由がなかったとしても、私は彼が恐ろしくない。 なぜなのかは、わからない。 「孟徳さま、勤務外ですよ。公のことで彼をいじめないでください」 文若殿が静かにたしなめる。 「おう。うまい酒じゃ。文若」 「そうでしょう。どんどんやってください。元直殿も」 「ありがとうございます」 「フン・・・・・・。文若、こやつはな、やる気ないのじゃ。覇気なしじゃ。才能があるのに、それを使おうとしない。腹が立つ」 「孟徳さま、また」 「うるさいわい。元直は戦がきらいだからな」 「好きな人がいるとは思えません。丞相は戦がお好きなのですか」 「おうよ。好きじゃ好きじゃ。戦場こそ我が心の故郷」 「孟徳さま、酔ってますね。そんなこと言ってなかったじゃないですか」 「この覇気なしにハッパかけとるのじゃ」 それはそれで、楽しい時間が過ぎた。 「元直、おぬし運が良いぞ。今日は新曲を持ってきたのじゃ。おひろめじゃ」 曹公はそう言って琴の前に坐った。私たちに目配せして、ニコリと笑う。 「元直、おぬしは戦がきらいと言う。もっともなことである。だがな」 最初の一音。 「うたは戦からも生れる」 震える波にさらわれる。魂に直接触れてくる感じ。 一瞬、断崖絶壁に立たされたかのような恐怖を覚えた。 この時間はなんだろう。 私は、いったい何者なんだろう。 裏切りなどどこにもなくて。 それなのに、いつもどこかが後ろめたくて。 (四) 母が死んだ。 朝食の仕度をしているときに倒れて、そのまま意識が戻らず、その日の夕方に息を引き取った。 南征の大編制が都を進発してから、半月ほど過ぎた日のことだった。 曹公が定めた法令にのっとって、葬儀は簡素に執り行われた。 私が紙銭を焼いていると、いつのまにか傍らに文若殿が立っていた。 「元直殿、よろしいですか。わたしもいくらか作ってきたんですよ」 手には、紙銭のいっぱい入った籠を持っていた。 「どうぞ。母もよろこびます」 文若殿は棺に礼拝し、私のとなりにしゃがみこんで紙銭を焼きはじめた。 この場に曹公がいなくてよかったと思った。なぜだか、そう思った。 文若殿が寄り添うようにして、一緒に紙銭を焼いてくれる。私のなかのなにかが、スウッと静まっていく感じがした。遠い昔の、平穏だったまるい場所に手が 届きそうな気がした。母が息を引き取ったその時から、心の芯が麻痺している私。モヤモヤとして、すべて幕越しに周囲を見ているみたいだった。それが晴れる ことはなかったけれど、文若殿のとなりは、心地良かった。 真っ白い喪服をまとい、化粧をしていない文若殿の横顔。氷片が解けるようにあっけなく燃え尽きる紙銭を見詰めている。文若殿はなにも話しかけてはこなかった。私もしゃべらなかった。言葉が出てこなかった。胸の底に錆び付いた涙があふれだすこともなかった。 錆び付いている。 それが実感だった。覇気がないと言われるのも仕方がない。 最後の客が帰り、私は疲れきって自室に引きこもった。寝台にゴロンと寝転がり、剥ぎ取るように履を脱いで放り投げた。脱力して溜息をつき、部屋に澱む薄闇をぼんやりと眺めた。 十六のとき、人にやとわれて仇討ちをした。 顔に白い土をぬりつけ髪をふり乱して逃走したが、役人に捕えられた。 姓名を尋ねられても私が口を割らなかったので、役人は車の上に柱を立てて私を縛りつけ、太鼓を鳴らして市場じゅうにふれまわった。私を知っていると名乗り出る者は誰一人いなかった。四日目の夜、仲間が縄を解いて助け出してくれた。 ぱっくりと裂けた膝の傷を紐でしばって逃げた。母を連れて、這いずりまわって逃げた。 弟に母をあずけ、名を捨て、剣を捨て、あてどなく流浪した。 荊州をさすらっているときに、山中で水鏡先生に拾われた。そして、孔明と出会った。 身体は疲れきっているのに眠れない。灯りをともす気にもなれない。 孔明。きみはどうしているかい。曹公が南下した。荊州は陥ちるだろう。きみは、あくまでも戦うんだろうな。俺たち、敵同士になっちまったな。曹公はきみを殺さないだろうけど、きみのことだ、捕虜になんかならないだろう。きみが勝ったら、曹公を殺すだろう。 俺はどっちも考えたくない。どっちも考えたくないんだ。 コトリ・・・・・・。 物音がした。居間のほうだ。私は息を詰めて起き上がった。鼓動が早くなった。 お母さ 辺りはすっかり闇だ。私は手探りで居間へと歩いていった。何も考えなかった。頭のなかは真っ白だった。なにかが潜んでいる気配がした。私はそれを願った。なにかいておくれ。不均等な闇。張り詰めた空気。 私の視界を、なにかがかすめていった。なにか、獣のようなもの。目を凝らすと、その姿がぼんやりと浮かび上がった。血に濡れてぬめった腕。泥にまみれ血にまみれ髪をふり乱し一振りの長剣を抱くように握り締め、虚ろな瞳の、なんだあれは、私自身ではないか。 白い闇が広がった。 足元が大きく歪んだ。 端から崩れていく。グラグラと揺れはじめる。立っていられない。 大地を踏み締める感覚がない。直角に下ろせなくて脚をくじきそう、でも、走らなければ。 背後から追いかけてくる。落ちる。落ちる。落ちる。闇に、虚無に、 呑まれる・・・・・・! 「文若殿・・・・・・!! 文若殿・・・・・・!!」 気が付くと、駆け出していた。 星空の下を裸足のまま走っていた。路がどんどん迫って来て、脚が勝手に前に出た。喪服が夜風を孕んではためいた。全速力なのに、走っても走っても息が切れなかった。 彼を呼んでいた。追ってきたのは狂気だったかもしれない。私は全力で駆けた。 文若殿・・・・・・! 彼の家の門にとりすがり、叩き鳴らし、叫んだ。 「荀令君! 文若殿! 後生です。入れてください! 徐庶です。徐 元直です・・・・・・!」 門戸越しに邸内で囁きあう人の声が響いてきた。足音。一度だけ、覗き窓が開く。 「徐 元直様、少々お待ちください」 丁寧な女の声が応えた。ほどなく、門が開いた。さやさやと風が鳴った。文若殿自らが風に吹かれて歩いてきた。彼が左手に持つ灯火の光が透明ににじんだ。文若殿は落ち着いた声で私にしゃべりかけ、そっと肩を抱いて中に導き入れてくれた。 「驚きました。悪漢に追われているのかと思いましたよ。どうなさいましたか、元直殿」 文若殿は、奥の間に私を落ち着かせ、向かい合い腰を下ろした。 「悪漢・・・・・・」 「顔が土気色です。横になりますか」 「それは私のことかもしれない・・・・・・」 「元直殿」 ふっと、意識が遠のきかけた。目の前の文若殿が見えなくなった。 ナゼ ワタシハ ココニイル? ナゼ ワタシハ カレ ヲ ・・・・・・どの。 「元直殿!」 「はっ・・・・・・」 急に焦点が合った。文若殿が心配そうに私を覗き込んでいる。 「お察しします。母君の死がこたえておられるのでしょう。お力になれれば・・・・・・」 私は、なんと言っていいかわからず、ただ首を横に振った。 「失礼します。お客様、お茶をお持ちいたしました」 女中が入って来て熱い茶を置いていった。 文若殿がわざわざ両手で湯飲みを私に手渡してくれた。 「かたじけない・・・・・・。いただきます」 一口飲むと、温もりが身体中にしみわたった。美味しかった。 「・・・・・・」 頬を涙がつたった。あとからあとから、流れ落ちた。そのまま声を出さずに泣いた。息を吸って吐くだけがせいいっぱいの泣き方だった。文若殿のあたたかな大きな手のひらを背中に感じた。 「私・・・・・・は・・・・・・」 胸の底にある塊をなんとか言葉でなぞろうとした。 なんとかして彼にわかってもらいたかった。 「来たくて許都に来たわけではな・・・・・・。母が、母を捕えられたから仕方なしに・・・・・・。母が死んでしまったら私は・・・・・・」 違う。そんなことじゃない。 「私はもうここにはいられません。曹公は、・・・・・・曹公のやり方は汚い」 違う。違う。なぜ? ずれていく。 「・・・・・・それは、移籍したいということですか」 「いや、謀叛です。ハハ・・・・・・。移籍など、曹公が許すはずもない。例えば」 もう駄目だと思った。失敗した。もう、どうとでもなるがいい。 「例えば、荀令君、あなたの首を持って西涼におもむき、曹公不在の許都を突くよううながす・・・・・・」 決定的だ。 文若殿はじっと私を見詰めた。存外、静かな目だ。 私の背中に当てた手のひらを決して離そうとしなかった。 「元直殿、わたしたちは、友ではないですか」 「友? 私の友は孔明だけだ」 「そうですか・・・・・・」 文若殿は、哀しそうに呟いた。 沈黙が降りてきた。 私は首を横に振った。両手で顔を覆った。 「すみません。あなたは親切な人なのにひどいことを言って。造反を口にした。首を打ってください」 「元直殿、今夜、一緒に寝ますか」 ・・・・・・。 は? 頭が混乱した。思考が停止して言葉の意味が理解できないのに、心臓だけが早鐘を打った。 「そ、それはどういう・・・・・・」 文若殿はクスリと微笑った。少し、悪戯っぽい笑みだ。 「造反といっても、お話になりませんな。狂言にしか聞こえない。だから、もう夜も遅いし、一緒に寝ませんかと言っているのです。おいやなら客用寝室を整えますが」 「いや、・・・・・・」 「いやですか」 「いや、いやというわけでは。でも・・・・・・」 私は次に言うべき言葉を必死に考えた。 「奥方に悪くないですか」 「なに考えてるんですか!」 「ハァ・・・・・・」 少し狭いですけど我慢してくださいね、と言って、文若殿は掛け布団を両手に持ってふわりと広げた。なかにもぐりこむと、日なたの匂いと心地良さに包みこまれた。文若殿の綺麗な顔がすぐ間近にあった。 半刻ほどしゃべって、それから灯りを消して、ウトウトした。 人と寝るとあたたかいものだなあと思った。そういえば、私はこの歳になるまで、こういうふうに人と一緒に眠ったことが一度もなかった。孔明とも。 たくさん、いろいろな夢を見た。どんな夢だったか、目覚めたときにはほとんど忘れてしまっていたけれど、全体としては、涼やかな草原に似ていたような。 そして今朝、私は空を見上げている。ずっと高いところを薄い筋曇が流れていく。 もうすっかり秋の空。 私の足が履いているのは、文若殿の履だ。 裸足で飛び出してきた私に、彼が貸してくださったのだ。 文若殿の履。品が良くて、やわらかくて、軽い。昨夜はとんでもないことを言ってしまったものだ。けれど、また逢いに行ける。今度は、これを返しに。 ただそれだけが命綱で、生きていけるような気がした。 昨夜の涙といっしょに、なにかがほどけ、流れ落ちたのだ。 不思議なことだ。もう私にこだわりはない。 今ならば、静かな気持ちで自分の過去を思い出すこともできる。 問題はなにひとつ解消してはいなかったけれど、なにかできそうな気分。 妻をめとるのも良いかもしれないと思った。 「おおーい、孔明。元気にやってるか。はりきって、やってるか。おまえ、絶対、死んだりするなよな。俺は、ほんの少しだけ、この地が好きになったぞ」 遠く南の空にそう呼びかけた。 そうして私は、奇跡的に軽い足取りで、待つ者のいない我が家へと向かい歩きはじめた。 |